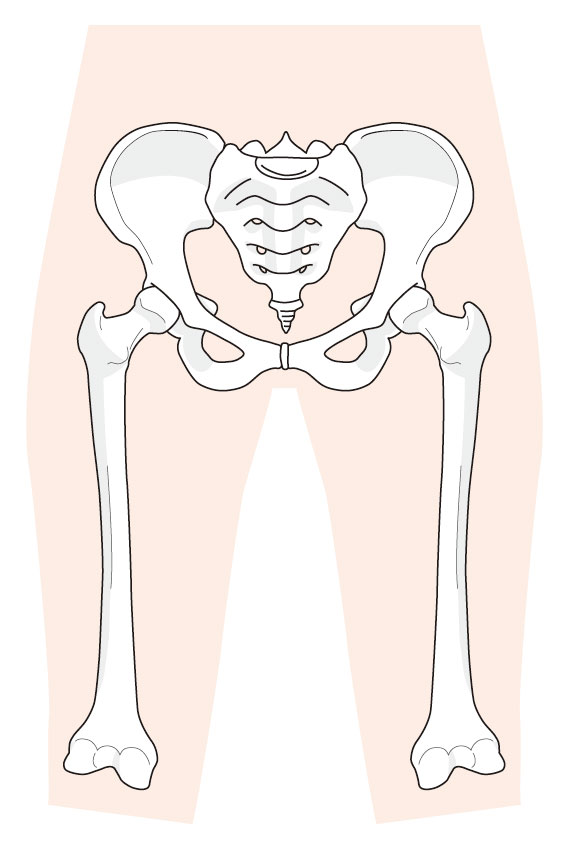まもなく夏の甲子園が始ますね。球児たちの熱い戦いが始まると、なんだかワクワクしてくるのは、私だけでしょうか。ひたむきな球児たちの姿を見ていると、胸が熱くなります。
ところで、この高校野球の聖地『甲子園』という名前が、実は「還暦」と同じように、干支(えと)に由来していることをご存じでしたか? 『甲子(きのえね)』とは、十干(じっかん)十二支(じゅうにし)の組み合わせで一番最初の干支。そして、還暦の『暦が還る』とは、その干支がひと回りすることを意味します。 今回は、甲子園や還暦をきっかけに、干支(えと)について話を進め、さらに、還暦を迎えた私の心境も述べさせていただきます。
1. 還暦って、そもそも何?〜「暦が還る」ってどういうこと?〜
まずは、十干(じっかん)です。
十干(じっかん)とは、「甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸」の10種類の要素のことで、十二支と組み合わせて「干支(えと)」を構成するものです。
★十干の成り立ちと意味
十干は、もともと古代中国で10日間をひとつの区切りとして、日を数えるために使われていました。この10日間の区切りは「一旬(いちじゅん)」と呼ばれ、今でも「上旬」「中旬」「下旬」という言葉として名残が残っています。
次に十二支(じゅうにし)。
これは、私たちが普段「子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥」として知っている、12種類の動物のことです。
★十二支の成り立ち
十二支は、もともと暦や時間を表すための記号として古代中国で使われ始めました。時間の単位として:一日を12の「刻(こく)」に分け、それぞれを十二支で表していました。たとえば、「子の刻」は深夜0時頃、「午の刻」は正午頃を指します。(「午前」、「午後」も、ここからきています。午(うま)より前は午前です。)
・・・方位の単位として:北を子、東を卯、南を午、西を酉とするように、方位を表すためにも使われていました。
その後、人々に親しみを持ってもらうために、それぞれの記号に動物が当てはめられました。これが、十二支に動物の名前が使われている理由です。
十干と十二支を組み合わせて、60通りの干支(えと)が作られました。古代中国でのことのようです。歴史書や戸籍、契約書などで年月を記録する際に使われました。
中学、高校の教科書レベルでも「辛亥革命」とか「戊辰戦争」とか、歴史上の出来事を干支で表している例はたくさんあります。
表にしてみました。
| 十干 | 十二支 | 干支 |
| 甲 | 子 | 甲子(きのえね) |
| 乙 | 丑 | 乙丑(きのとうし) |
| 丙 | 寅 | 丙寅(ひのえとら) |
| … | … | … |
| 辛 | 酉 | 辛酉(かのとのとり) |
| 壬 | 戌 | 壬戌(みずのえいぬ) |
| 癸 | 亥 | 癸亥(みずのとい) |
| — | — | — |
| 甲 | 子 | 再び甲子に戻る |
この表の十干は縦に6回、十二支が縦に5回入れていくと、また、最初に戻ります。10と12の最小公倍数ですね。
私はウサギ年(卯)ですが、5種類のウサギ年があるということになります。
1963年は癸卯(きぼう/みずのと・う)、1975年は乙卯(おつう/きのと・う)、1987年は丁卯(ていう/ひのと・う)、1999年は己卯(きぼう/つちのと・う)、2011年は辛卯(しんぼう/かのと・う)
2023年に癸卯に帰ってきました。還暦です!!
お気づきの人もいると思いますが、十干は10あるのに、うさぎ年は5種類。
つまり、のこり5つとは組めないんですね。
1 甲・2 乙・3 丙・4 丁・5 戊・6 己・7 庚・8 辛・9 壬・10 癸
横に並べて番号を付けたら、偶数のものとしか組めないのです。
実は、十干は陰陽道で奇数が陽(兄・え)、偶数が陰(弟・と)ということになっています。ウサギ年は、陰の(弟・と)としか組めないということです。
ちなみに私の3つ下の弟は、丙午(ひのえ・うま)の生まれです。(あまり評判のよくな干支で、実際その年の出生数は少ないということを聞いたことがあります。)
午は、陽(兄・え)としか組めないということになります。
干支を順番に見ていくと、「~え・〇」「~と・▽」「~え・◇」「~と・□」という具合に、
~え=兄、~と=弟が交互に出てきます。
あなたの干支は何でしょうか? 十二支だけでは本来、干支とは言えないんですね。
2.甲子園と干支、そしてその特別性
甲子は、その組み合わせのトップバッター。いろはの「い」。「一丁目一番地」です。
背番号1と同様、特別感があります。
甲子は古代中国でも特別視され、政治的・宗教的な儀式が行われることもあったそうです。
日本でも「甲子の日」は吉日とされ、商売繁盛や開運祈願の日として今も使われているそうです。
さて1924年(大正13年)甲子の年の8月1日、甲子園大運動場は完成しました。
当時の阪神電鉄は、甲子の年に合わせて球場を建設することで、地域の発展と縁起のよさをアピールしようとしました。オープニングでは、阪神地区の小学校から集まった2500人の児童による体育大会が開催されました。
単なる球場ではなくて、地域の夢と希望を象徴する場所として誕生したのです。
今では、「甲子園」という言葉は、特別な意味を持つようになりました。高校野球の感動が他の分野へも波及したということだろうと思います。
高校生の取り組むものに「甲子園」が使わるますね。
思いつくだけで、ダンス甲子園、写真甲子園、俳句甲子園、スイーツ甲子園、ファッション甲子園が上がります。
調べてみると、科学の甲子園、書道パフォーマンス甲子園、アプリ甲子園、囲碁の甲子園、キャリア甲子園なども見つかりました。ほかにもまだ、あるだろうと思います。
この特別な「甲子園」の出どころは、東洋文化の知恵ともいえる、干支だったんですね。面白い。
3. なぜ「赤」なのか?還暦祝いに欠かせない色の意味
話は、還暦に戻りますが、、、
私は、ブログのアドレスを見てもわかる通り、1963年生まれです。癸卯(みずのと・う)。
次の年、1964年は東京オリンピック。甲辰(こうしん/きのえ・たつ)。この干支は始まりの「甲」と勢いのある「辰」が組み合わさって、新しい挑戦や発展を象徴する年ともいわれるようです。
このあいだ、2023年にふたたび、癸卯(みずのと・う)がやってきました。生まれてから60年たったということです。
「還暦には赤いちゃんちゃんこ」というイメージがありました。しかし、私は(おそらく、多くの同い年の人たちも同様に)赤いちゃんちゃんこを自分事とは考えられませんでした。家族も同じような感性を持っています。
ただ、妻は「赤」の力は信じているらしく、赤いパンツと靴下をプレゼントしてくれました。
魔除け・厄除けの色
古くから赤は邪気を払う色とされ、病気や災厄から身を守るために使われてきました。
鳥居が赤いのも赤飯の小豆の赤も、魔除けの意味があります。
還暦は厄年の一つであるため、赤を身に着けて厄を払い身を守るということです。
生まれ直しの象徴・・・赤ちゃんの産着から「ちゃんちゃんこ」
還暦は「生まれ直し」とされ、「赤ちゃんに戻って人生をやり直す」という意味が込められています。
赤ちゃんが着る「赤い産着」にちなんで、赤いちゃんちゃんこや帽子を贈る風習が生まれました。
昭和の時代くらいまでは、生まれ直しという言葉を使いながらも、現実的には長寿の節目で、残り少ない人生を気楽に過ごしてほしいという意味があったように思います。(個人的見解です)
平均寿命がどんどん伸びて行って、還暦は「もうそろそろ終わり」ではなくなりました。
明確な統計的はないものの、ギフト業界や還暦祝い専門サイトの調査では「赤いちゃんちゃんこを贈る人は減少傾向にある」と報告されています。赤い「シャツ」「ネクタイ」「スカーフ」など実用的なアイテムを贈る傾向が強まっているそうです。
還暦とは
【以前】「生まれ直し」=産着「ちゃんちゃんこ」⇒⇒⇒【今】「折り返し」=まだまだ現役「実用的アイテム」
4. 還暦はゴールじゃない!第二の人生を始めるための大切な節目
就職したのは、昭和の終わり。バブルの始まりといわれる1986年。
経済的な心配あまりありませんでした。
そのころ、還暦といえば何を連想したか言うと、「定年退職」と「年金受給開始」でした。
当時、還暦と人の働き方、社会福祉のあり方がかみ合っていたと思います。
60歳=還暦=退職=年金受給開始
年金受給が60歳ではなくなった時から、還暦の重みはどんどんなくなってきたように思います。
いざ2023年、私も還暦を迎えましたが、その時点で年金受給まで5年ありました。
今も再雇用で働き続けています。幸い、働くのは苦ではないので(給料の少なさは別にして)、生活はできています。
還暦をどうとらえるか
東洋の知恵、干支。甲子から始まる60組の言葉。
60年で一周するというこのサイクルは、ある時期、私たちの生活にフィットしていたと思います。今も、すっかりその意味がなくなったとは思いませんが、一時期よりも、かみ合わなくなってきたのは確かだと思います。
であるなら、私たちは還暦をどうとらえていくべきなのか。
これまでの先輩方とは違って、意識的に還暦に向かわなければならないと考えます。
一つは、60年使ってきた肉体を総点検する時期ととらえること。
多くの先輩が異口同音に言うのは、「健康」が最も大事だということ。
私の場合は、2024年、十数年ぶりに歯科に行きました。
ギリギリ手遅れになる前に治療ができました。
そのほか、脳ドックも進められましたが、まだ行っていません。
もう一つは、手取りの収入が下がり始める地点ととらえること。
生命保険は大胆に見直し、ほとんど解約しました。
スマホ料金、インターネット料金の見直し。
多くの場合、還暦時点の収入がピークだと思います。
退職金がある場合は、その生かし方、使い方を計画する
私は「投資」に舵は切れませんでした。
もっと早くから積立NISAとか、投資信託とかやっておけばよかったなと思ったこともありましたが、仕方がありません。お得な定期預金などは低リスク低リターンで安心ではあります。
ハローワークへ行ってみた
還暦を過ぎると、門は狭いですが、まるっきり雇用がないわけではないことがわかりました。
再雇用にしがみつかなくてもいいのかな、という気持ちにもなりました。
金額は物足りなくても、新しいことに挑戦できるというのは、面白いと思います。
新しい趣味を始めるよりも、刺激的のような気がします。
家族の理解が必要ですね。
企業に問い合わせ電話はまだしたことがありませんが、いくつか候補を温めています。
世界が広がったような気がして・・・・
これが一番のおすすめです。